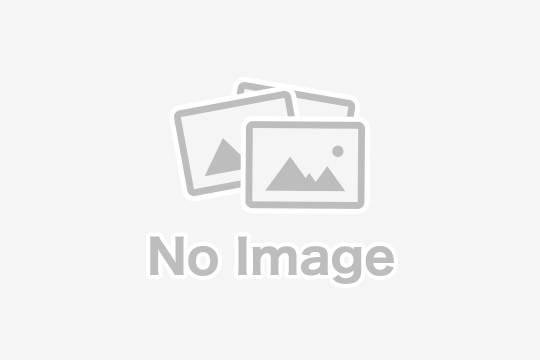- 堀田圭江子/音楽療法セラピスト®、音楽療法士、産業カウンセラー

- 洗足学園音楽大学 声楽家卒業。高校教員を経て音楽療法士となる。
30年以上の音楽療法の臨床経験を生かし「音楽療法セラピスト®養成講座」を主宰。
音楽療法セラピストを志す後進の育成にもあたっている。
音楽療法士の堀田です。
さて、 前回のへそ踊り…ではなく
音楽療法のへそ(大切な部分)についてお話しました。
本日は
私の失敗例を通して記録の重要性とその活用についてお話しますね。
特別養護老人ホームに入所している82歳女性の認知症の方がいます。
軽い脳出血の後遺症もあり、話すのには時間がかかりますし
右手の麻痺が少しだけあります。歩行は杖を使い自力でできます。
彼女は、音楽療法のセッション中は落ち着いて着席し
こちらの指示も理解して、歌のプログラムや楽器のプログラムも
意欲的に参加していました。
そんなある日
施設職員さんからこんなことを聞かれました。
「先生、○○さんが最近スプーン持てなくなってきているんだけど、
音楽療法で楽器とか持てるの?」
それで私は
「太鼓のバチは持ててるけど…。でも…いや、持ち方前と違う気がする!
ちょっと記録見てみるから、少し時間くれる?」
と言ってワーカー室に飛び込みパソコンに入っている記録を探しました。
さてどうでしょう。
なんとそこには大きな変化ではなかったのですが
「右手で握ったバチを2回床に落とした」
という文章が2ヶ月前に記載されていたのです。
私は 「ほんとだ…。兆候があった…。」と愕然としました。
そして
さきほど質問してきたワーカーさんにその記載を伝え
問題を見落としていたことを詫びました。
それからは
セッションで起こったどのような小さい変化でも記録するだけでなく
言葉でも施設職員に伝えるようにしました。
■そのおかげで
利用者さんたちの変化にすぐに対応できるようになり
急激に症状や状態が重度化する人が少なくなっています。
■また、
認知症や進行性の病気の方々が
現状維持されているという効果にもつながっていると思います。
私はいつもセッション終了後ミィーティングをし
その日のクライアントさんの様子や反応を記録し評価しています。
■しかし
今回の失敗のような「見たつもり」=「記憶が定かではない」ことは
少なくないと思います。
また、 時間がたてば記憶は薄れていくものです。
■そんな時こそ
記録が後で役にたちます。
そして
せっかくとった記録や評価をそのままにしておくのはもったいない。
記録や評価は大切なクライアントの変化のプロセスであり
治療の方向性を決める資料にもなります。
■この資料を活用すると
治療効果を上げられますし
セラピスト自身も自分の診たての傾向や使用する楽曲のクセがわかり
自己成長の助けにもなります。
記録って本当に宝物なんです。
どうぞ、 私の失敗を参考にあなたも記録や評価をつけて
活用してみてください。
今の現場仕事の内容の見直しや、問題点の解決に必ずヒントにもなるはずです。
記録と評価についてさらに詳しく知りたい方は、
音楽療法セラピスト養成講座 「記録と評価」にて詳しくお話ししますので
ぜひいらしてください。
では、今日はこのへんで。
音楽療法士 堀田圭江子